2月29日(水)、昨年の東日本大震災で大きな被害を受けた仙台市の沿岸部、若林区の荒浜地区を訪れた。前日の28日に仙台市内で開催された「三方良しの公共事業改革推進カンファレンスin仙台」(写真1)に併せて、翌日に被災地の見学を計画して欲しいと事前に事務局に依頼し実現した。
荒浜は、地震発生直後、大津波が渦を巻きながら濁流となって、見る見るうちに家や車、漁船を押し流し、堤防のように見える盛土された道路に向かって狂ったように進んで行く、我が目を疑うような映像が何度もテレビに映し出された地区である。後で知ったが、この荒浜地区では翌日200人〜300人の水死体が見つかった。
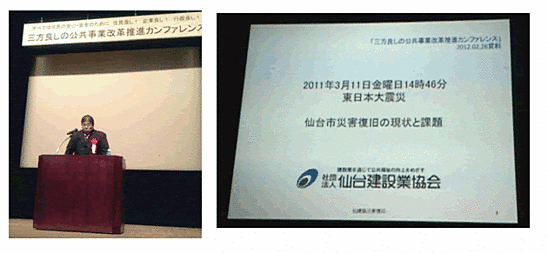
仙台駅を出発した車が荒浜に近づくにつれて、半壊した建物(写真2)が見え始めるが、次には、がれきが取り除かれ、ほとんど何も建っていない荒涼とした平地となる。見えるのは、家の基礎コンクリートだけの宅地と道路だけ(写真3)。そんな風景を見ながら、地震の翌日から全社挙げて復旧作業に当たった仙台市の深松組社長のカンファレンスでの事例報告を思い出す。



テレビや新聞では、自衛隊や消防団員などによるがれきの中の遺体の捜索状況がたびたび報道されたが、捜索隊が被災地に入れるように最初に道路を開けた(写真4)のは、すべて地元の建設会社であった。自らの会社も被災し、社員が亡くなったり重機を流失したりした建設会社も、残った社員を動員して作業に当たった。がれきに埋まった道路にも遺体があるので、遺体を発見した時は重機で傷つけないようにしながらの作業であったが、その後、作業に当たった多くの社員がうつ病になり今も苦しんでいるという。

コンクリート基礎の上に建っていた家々でそれぞれの日々を送っていた人たちは、今、生きておられるのだろうか、どうされているのだろうかと思いながら海岸に着いた。海岸には、基礎をえぐられながらも残った公衆便所(写真5)のそばに慰霊碑(写真6)が建っていた。海岸の堤防(写真7)に登ると、何か臭う。海岸沿いには水産加工場があったので、その臭いだと聞く。
堤防の上で、一緒に視察した奈良の中村建設の社員さんから、炊き出しなどのボランティアで被災地を4回訪れたと聞き、義援金や会津若松への震災支援旅行くらいしかしてこなかった自分を恥ずかしく思った。



昨年の3月11日の午後2時48分、私は午後1時から本社の4階で行われていた「現場NOTE」導入プロジェクト会議に最初の1時間だけ出席してから、2階の自席で仕事をしていた。大きな揺れは感じたが、近所のビルの解体作業がその時だけ特に激しかったのだろうと思っていた。富山県では全く被害が無かったが、私がこの時間に出張や旅行で東北地方に出かけていてこの大震災にあった可能性が全くないとは言い切れないと思うことがある。実際、車で仕事に出かけていて、迫り来る津波から命からがら逃げた人のニュースを聞くと、私を含め被害にあわなかった全国の人々は、たまたま地震の影響をさほど受けない安全な場所にいて、たまたま生き残ったと思えて仕方が無い。
大震災から一周年を迎えるに当たって、3月に入ってから連日テレビや新聞は被災地の様子を報道したが、見るたびに読むたびに、被災地でこんなにも悲惨な出来事があったのかと思った。また、未だに精神的にも経済的にも厳しい生活が続いていることに、何とも言えない悲しさに襲われた。
そして、自分の想像力の無さに愕然となった。
生き延びたのに仮設住宅で自殺した50代の女性。4歳の息子を失い自殺を考える日々を送る女性と、娘であるその女性を見守る自らも妻を失った私くらいの年齢の父親。それまでの地域のつながりを失った仮設住宅での生活で、引きこもりになったお年寄り。両親を亡くした孫を育てながら、当初は死にたいと思っていたのが、今ではあと10年あと15年、いや90歳まで生きてひ孫の顔を見たいと話すおばあちゃん。そんな話を見聞きするたびにティッシュペーパーに手を伸ばし、そんな状況が生まれるであろうことに想像が及ばない自分、毎日「今日の昼は何を食べようか?」、「今夜はすき焼きが良いな」などと気楽なことを考えながら生きている自分を恥ずかしく思った。
日本人は忘れっぽい国民だといわれ、私自身もその傾向が強いが、2万人近くもの死者、行方不明者を出した東日本大震災は、死ぬまで絶対に忘れてはいけないと思っている。この大震災で亡くなった方々、被災されて厳しい生活を送っておられる方々のことを忘れることなく、自分の人生の責務は何か、その責務をどのように果たせばよいかを考えながら生きていきたい。

津波で被災した閖上(ゆりあげ)中学校
いつか復興して、この地で生徒達が会える日が来ることを願います。
1月29日(日)、雪での遅れを考慮して1便早めた午前11時10分発の飛行機で、富山空港から羽田に向かった。私が所属している富山みらいロータリークラブ(RC)の姉妹クラブであるオーストラリアのケントフォーストRC訪問と、バヌアツ共和国への3度目の支援と確認の旅の始まりである。
19:50成田空港発のカンタス航空22便で日本を発ってシドニー空港に翌30日(月)の朝7:30(日本時間5:30)に到着。我々RC会員7人とその娘さんや娘さんの友達4人の11人は、空港に迎えに来てくれたケントフォーストRC会員の案内で市内観光した後、ケントフォーストに向かう。ホームステイ先のケントフォーストRCの5人のメンバーの家にそれぞれ分かれ一休みしてから、ケントフォーストRC会員の一人の大邸宅でのクラブ例会(我々の歓迎パーティー)(写真1)に向かう。このパーティーで、私は今年6月5日に開催する我々のクラブの設立15周年パーティーへの参加依頼のスピーチをおこなう。私より英語の上手なメンバーがいたのだが、1999年にを訪れて姉妹クラブ締結交渉を初めて行った者として、またクラブ会長経験者ということで私が挨拶した。(写真2-1)ホームステイ先のホストのKeith(キース)さん(写真2-2)に教えてもらった挨拶での切り出しの言葉「Unaccustomed as I am to public speaking」(たぶん「公式な挨拶は私は不慣れなのですが」という意味)は、Keithさんの予測通り笑いを誘った。

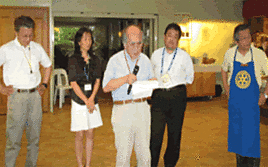
翌日の31日(火)は、3人のホストファミリーの車に便乗して、ブルーマウンテンの観光(写真3-1)に向かった。そこでの昼食時に聞いたホストファミリーの一人のGil Kommer(写真3-2)さんの言葉が忘れられない。それは、「人生は毎日の続きであり、過去や未来を恐れることは無い。何事も常に変わり、意識を変えることを恐れてはいけない。」というような話だ。
この話から、私は今年の当社新年式で話した「目が覚めたら朝だった」という、砺波に住むお百姓さんの言葉を思った。朝、目が覚めるのは当たり前だと思っているが、それは生きているから目が覚めるのであり、今日も生きて一日を過せることに感謝しようということなのだ。さらに私は、これからは今日一日を悔いの無いように生きたい、と話したのであった。毎日をシッカリ生きることの大切さを、Gilさんの話で再認識させてもらった思いである。
このGilさんは、姉妹クラブについて協議した時のケントフォーストRC側の3人の内の一人だが、その時にも、「赤ん坊は歩きだす前に、ハイハイする」すなわち、何事も段階を追って進んでいくことが大切、姉妹クラブの関係も同じで、最初は手紙やビデオのやり取りから始まって、お互いのクラブの訪問に進ばよいという話をされたことを思い出した。
ブルーマウンテン観光の後は、2つ目の目的地バヌアツ共和国への移動であるが、2006年に初めてバヌアツ共和国に出かけたときと行きも帰りも同じ行程であった。夕方フェリーでケントフォースとからシドニーに向かい(写真4)、シドニーのホテルに泊まる。翌日2月1日(水)は美術館でピカソ展(写真5)を見たり、大聖堂(写真6)を見学したりしてから午後8時過ぎのバヌアツ航空の飛行機で3時間半かけて、バヌアツ共和国首都ポートビラ(エファテ島)に真夜中に到着。その時と同じホテルに泊まり、翌日2月2日(木)の早朝、ポートビラ空港から50分間のフライトでエスプリッツ・サント島に向かう。(写真7)






このサント島のベネという村にケントフォーストRCが妊産婦のための診療所を国際奉仕事業として建設していたが、その増築工事に我々のRCも資金提供したのがきっかけで、2006年12月に初めて、名前も知らなかったバヌアツへの現地視察に出かけた。その時のメンバー4人が、2009年8月の2回目、そして3回目の今回も参加したのである。
3回目のバヌアツ視察に、当初私は参加する気はまったく無く、ケントフォーストRC訪問だけで帰国するつもりであった。しかし、昨年11月に行われた夜のクラブ例会で、バヌアツに1回目も2回目も一緒に行った3人が座っているテーブルに酒を注ぎに行ったら、「林さんも行きましょうよ」と強く誘われ、気が変わったのであった。
サント島に着いた我々は、空港近くの町ルーガンビルで日本人が経営しているレストランで朝食をとってから、これも最初の訪問の時と同じくバッテリー(パナソニック製であった)を調達し、10時半ころ専用車で目的地のベネとホグハーバーに向かう。



ルーガンビルからのアスファルト舗装された道はしばらく走るとでこぼこの土の道に変わり、雨でぬかるんだりしていたのが(写真9)、今回は終着地のホグハーバーまで幹線はすべて舗装されていて、センターラインも引かれ(写真10)、交通標識もあちこちに立っていた。インフラ整備の状況に関しては、2回目の訪問の時は、携帯電話が使われていたのに驚いたが、今回の驚きは目的地まで舗装された道路や何箇所かで行われていた道路や橋の工事であった。これでは、当社がバヌアツに進出する余地がどんどん少なくなると思った。しかし、道路に沿って建てられた電柱は途中で途切れ、前回の視察で泊まったロンノックビーチには相変わらず電気が通じておらず、ホテルに備え付けの発電機からの電気も夜10時前には前回と同じように止まってしまい、夜中に使ったトイレはタンクに水が溜まらなくなってしまった。
シドニーで別れた4人以外の、男性5人と女性1人の6人の富山みらいRC会員(私が65歳で最年長)と会員の娘さん1人、そして毎回お世話いただいているケントフォーストRCの73歳のネイビルさん、そして運転手の53歳のイノックさんの9人を乗せ、さらに現地で配る古着のTシャツを詰め込んだ大きなカバンを積んで、ワイドサイズのハイエースは順調に走り、11時にはベネ診療所に着く。我々のために朝食を用意して(写真11)待っていてくれた住民のおばさんや子供たちに私が簡単に挨拶して、食事を頂く。1回目の訪問でもこの場所でTシャツを配り喜ばれたが、今回もたくさんのお母さんやおばあちゃんが1枚1枚手にとって品定め(写真12)しながら受け取られた。




その後は、2回目の訪問で富山みらいRCがソーラ発電機やパソコン2台を贈って支援しているホグハーバーの学校へ向かう。プロジェクターと追加のパソコンをそれぞれ1台贈呈し、電気関係の仕事をしている戸田さんとパソコン関係の仕事をしている吉田さんが、校長室に置かれているバッテリーの点検やパソコンの設定を行ったり(写真13)、教室ではプロジェクターで英語版の「日本昔ばなし」の中の桃太郎を写したりした。(写真14)プロジェクターは、これまではパソコンを取り囲んで生徒が画面を見ていたが、これでそのようなことはしなくてすむと大変喜ばれた。しかし、前日までずっと続いていた雨のためにソーラーからの電気がバッテリーに十分に貯まっておらず、数分間で電気が切れ映像が消えてしまった。電気があるのが当たり前の日本と比べようも無い状況を目にし、文明の発展とインフラ整備の関連性を思った。


翌日は小雨の振る中をシャンパンビーチ(写真15)に出かけ、途中の浜茶屋(?)ではヤシガニ(写真16)を食べ、過去の2回に訪れたのとは違うブルーホール(写真17)を見学してから、渡し舟でオイスターアイランドに渡り、最後の夜を過した。オイスター(牡蠣)という島の名前だけあって、夕食に食べた生牡蠣は絶品であった。生ものはあまり食べないほうが良いよいと出発前から言われていたが、私には関係の無いこと。ケントフォースとでもシドニーでも牡蠣を生でたくさん食べたが、それぞれに味が違っていたことが今回の発見である。



翌2月4日(土)の朝、ネイビルさん(写真18)とサント空港で別れ帰国の途に着き、シドニーから夜行便で成田に戻り、5日の日曜日、今度は予定より1便早い飛行機で羽田から富山に無事到着した。妻から1月31日に、富山が大雪だと、家の前の雪の山に座っている我が家の犬の写真付きのメールをもらっていたので、富山空港に降り立って見た雪にビックリはしなかった。
今回の旅では、往復の飛行機の中で宇野千代さんの「天風先生座談」を読んだが、オーストアリアでGilさんから聞いた話やバヌアツ共和国での見聞と思い合わせて、これからはもっと積極的な生き方をしなければいけないと強く思った。よい旅であった。

昨年11月のこのコラムのタイトルは「65歳」であった。昨年の11月に行った中学校の同期会での自己紹介の模様と、65歳以降の生き方について次のように書いている。
「男性の自己紹介では、私ともう一人がオーナー経営者、もう一人がそれに近い立場、また二人が開業医で、この5人が現役で毎日働いていた。しかし残りの7人は、会社を定年退職した後、同じ会社か関連会社で再雇用や嘱託として働いていたが、昨年64歳で、あるいは今年65歳になって完全に会社を離れ、年金生活になっていた。たまにアルバイト的に以前の会社を手伝っている人もいたが、「毎日サンデー」のようで、現役のころは精力的でギラギラしていた男性も、とても穏やかになっていたし、他の男性からも、リタイアするとこんな感じになるのかと思わされた。(中略)
早生まれの私は、かろうじてまだ64歳だが、今回の同期会ではこれまでのように再会を懐かしむことに加え、一般的に高齢者といわれる65歳から先の生き方を考えさせられてしまった。(中略)
今回の同期会での男性たちの話を聞いて、やはり、働いていることの方が私の性分にあっていると思った。建設業にとっても介護事業にとっても非常に厳しい経営環境ではあるが、私が参加している勉強会の合言葉“75歳、現役バリバリ”を実践すべく、富山の社会基盤整備や維持のために、また、富山のお年寄りの幸せのために、がんばって仕事をしたい、そのためにも、もっともっと勉強しなければいけないと思った。」
そしてこの正月2日に私も65歳になった。この日の午後から新年式での年頭挨拶で使うパワーポイントの作成を始めたが、スライドには入れないけれども、どうしても挨拶の冒頭に紹介したい言葉があった。それは「目が覚めたら朝だった」という、私のメモ帳に書きとめていた言葉である。
どこでこの言葉を目にしたのか、あるいは聞いたのかは定かではなく、「砺波のお百姓さんの砺波さん」とコメントが付いているだけだったが、昨年末にこのメモを見つけたとき、なぜメモしたか直ぐに思い出せた。朝になったら目が覚めるのは当たり前と思うかもしれないが、目が覚めるということは今日も生きているということであり、生かされているということである、というような説明に、高校の同期で社会人になってからも交流があった女性が、布団の中で亡くなっているのを、朝、お姉さんが発見したという話を思い出し、この言葉に共感してメモしたのだった。
昨年末にこのメモを見つけて読んだときは、東日本大震災の翌日の3月12日の朝、2万人以上の方が目を覚まさなかったのだと思った。そして改めてこの言葉の重さを感じた。その翌日から毎朝、目を覚ますと「ありがたい、今日も生きている」と思うようになった。
現在世間では定年を60歳から65歳に引き上げている段階であるが、大企業でも55歳が定年退職であった昭和49年から当社は65歳定年である。私が一般社員だったら65歳の誕生日をもって定年退職となるので、昨年末に退職手続きを済ませてしまっていて、1月4日の新年式には出席しなかっただろう。しかし役員であるがゆえに65歳を過ぎても新年式で挨拶し、今日も当社で働いておられるのである。生きていて、65歳を過ぎても働く会社があり、働くことが出来るということは、何と素晴らしいことだろうか。そのことに対する感謝を忘れず、今年の経営指針の第一番目に掲げた「誠実に、勤勉に、汗を流し、効率よく働く」を、社長である私自身がシッカリ実践しなければいけないと思いながらスライドを作っていった。
聖路加国際病院理事長の日野原重明先生は、今年101歳を迎える自分にとって、新世紀への約束、決意=コミットメントをすることが、自分に与えられた使命であるとして、「日本から武器をなくすことこそ、世界平和への第一歩だと信じ、110歳まで生きて、この運動に全力を注ぎたいと考えています。こうした活動への賛同者をひとりでも多く得るためにも、65歳以上を老人とせず、少なくとも85歳までは自立した生活が続けられるよう、健康運動のキャンペーンを日本中に広げたいという思いも新たにしています。」と「100歳・私の証 あるがまゝ行く」(朝日新聞1月14日)に書いておられた。
その日野原先生が会長を務める「新老人の会」の富山支部世話人代表の私なのだ。65歳になったからと言って、前期高齢者になったとは全く思っていない。私が大事にしている、“「働く」は「端・楽」=周り(端)を楽にする=世のため人のために役に立つ” ことを、会社経営を通じて実践するために、朝目覚めたら、生きていることを自覚し感謝することから一日をスタートさせる、これが65歳の誕生日以降、日々思っていることである。
